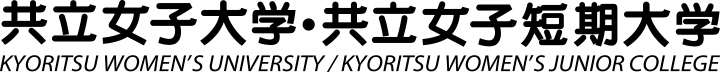文芸学部取り組み?プロジェクト紹介
更新日:2016年04月10日
文化専修
受験生へのメッセージ(上野 愼也)
過去の在り方とポリス社会の構成/前四世紀アテーナイ社会の言説空間
古代ギリシア、西洋史学、西洋古典学、ギリシア語、ラテン語
文芸学部にまなぶ偶然と必然

人生には色々と不思議なことがあるようです。私が古代地中海世界、とくに古代ギリシアの言葉や文化に首をつっこむようになったのも、全くの偶然です。
西域の歴史や、漢籍を繙く将来を夢見る少年でした。小さい頃から漢字に親しんだせいか、漢字がビッチリと並んでいるのを眺めるのも好きでした。「日中国交正常化」の影響もあって、しきりと「日中友好」が謳われる時代の空気を胸いっぱいに吸い込んでいました。
偶然その一: 再会

転機は『論語』との再会でした。親しみやすい訳文を載せた単行本を見つけ、軽い気持ちでひもといてみました。直前に講談社学術文庫の『大学』というちいさな本を読んで、儒学の系譜が気になってもいました。見慣れた文、共感を抱く文が次々に現れ、楽しい読書でした。『論語』って、こんなに愉しい書物だったんだな。自分の価値観と、こんなに重なり合う本だったんだな。そんなことを再確認したところで、はたと気がつきました。
──ここまで自分にべったりのものを、どうやって勉強して行けばいいんだろう。椅子に座り、足を浮かせて、その椅子を自分の腕の力だけで持ち上げようとするようなものじゃないか。それに、勉強して何になるんだろう。再確認の快楽をなぞり続けるだけではないのか。
あれからもう、随分と時間が経っています。あの時の気持ちを、いま、こうやって言葉にしてみると、あまりに浅はかで、短絡的な考え(?)に、我ながら恥ずかしくなってしまいます。その一方で、今も変わらない、心棒のようなところも顔を見せています。共感に対する警戒心といいましょうか。共感しているような気がするけれど、ほんとうに共感しているんだろうか。どこまで対象を理解しているんだろう。いや、そもそも共感ができたとして、それでなにかが判ったことになるんだろうか、と。依怙地といいますか、ひねくれているといいますか。
偶然その二: 邂逅

ちょうどその頃、岩波文庫でヘーロドトスの『歴史』を読みました。松平千秋先生の平明な訳のおかげで、今まで自分とは全く縁のない、地中海やオリエントの古代がぐっと身近になりました(世界史で名前だけ習う書物が面白いわけないだろうと思うかも知れませんが、まあ一度、開けて見て下さい)。共感することなど、まずおぼつかない世界に興味を抱いたのは、野次馬根性旺盛なヘーロドトスの筆のおかげかも知れません。これは是非、原文を読んでみたいと思い、岩波文庫版の扉の裏を見ると、
Herodotus
HISTORIAE
と書いてあります。当時、古代地中海に複数の有力言語があったことなど知るよしもなく、「ヒストリアエ」とローマ字読みしてみて、「アエ」で終わっているのは、古代ローマの言葉(ラテン語)だな、と、以前読みかじったローマ史の通俗本に出てきたカタカナを思い出しながら、独り決めしました。
早速なじみの大型書店へと足を運び、語学書の棚を見て、ラテン語の入門書を探しました。以前、岩波全書の入門書を見かけたことがあるので、それでいいだろうと思ったのですが、その日、生憎と棚にその本がありませんでした。まったく同じ装丁で、ギリシア語の入門書がありましたから、ラテン語じゃないけどまあいいや、折角来たんだから、これでも買って勉強するか、単語を覚えたら、英語みたいなものだろう──と、べらぼうな了見で本を買ったのが、古代ギリシア語との出会いです。東洋学、漢学に志した大学受験の結果がいまひとつで、浪人を決めた年のことでした。
運命に魅入られて

ヘーロドトス『歴史』の冒頭部分。本文
の三行目に「驚嘆すべきこと」という字
が見える。
欧米は嫌い、英語なんか大嫌いという少年が、欧米の根底を形作る古代ギリシア文化の言語を独習しようというのですから、今思えば何かの縁だったとしか言いようがありません。幸い、古代ギリシア語は「英語みたいなもの」ではなかったので、すぐに勉強をやめるようなことはありませんでした。ヘーロドトスの著作がラテン語ではなく、ギリシア語で書かれていることもじきに判り、それがまた発憤材料になったのかも知れません(ギリシアの文物をラテン語で表記する習慣を知るのは、もう少し後のことでした)。その後、しばらくはヘーロドトスから遠 ざかり、哲学者プラトーンの書き物や、歴史家トゥーキューディデースの『歴史』をかじったり、弁論家と呼ばれる人々の作品を繙いたり、また 金石文などをいじったりしました。ヘーロドトスと真面目に向き合おうと考え出したのは、ようやくここ数年のことです。
驚嘆の言語と他者

デルポイのアポッローン神殿で人は己
を待つ運命を神に尋ねた。
古代ギリシア語は多分、習得するのが難しい方の言語です。英語で‘It’s Greek to me.’ といえば 「ちんぷんかんぷんだ」という意味になります(フランス語やドイツ語、現代ギリシア語で「ちんぷんかんぷんだ」は「私にはそれは中国語だ」、イタリア語だとそれがヘブライ語だのトルコ語、アラビア語となりますけれども)。死語だからということもありますが、記憶するべき文法事項が多く、修辞技法の蓄積も分厚く、それに死語になるまで千数百年の展開があるだけに、内実がかなり多様だということもあります(万葉集の成立がいまから1,250 年くらい前のことなので、比べてみて下さい)。それでも勉強を続けたのは、難しいことなら、なおのことやってやろうというひねくれ者なりの気概があったからなのかも知れません。しかし、そればかりではないと、今は思います。ひとつは(内実を平たく説明するのが難しいのですが)完成された言語であるということ、それから今ひとつは、共感できないもの、未知のものに対する瑞々しい感性に育まれた言語──あるいは、「驚嘆(タウマ)」を駆動力とする文化を育んだ言語であるということです。
共感に対して警戒心を抱く私が何の共感も、接点もなかった古代ギリシア語に手を出したところ、それが共感の難しい相手に対する野次馬根性旺盛な文化を育み、これに根ざした言語でした。出会いのきっかけとなったヘーロドトスは後代「歴史の父pater historiae」と呼ばれ(かつ、同時に「作り話の父pater fabulae」と揶揄もされ)、その一方で来たる人類学のさきがけとなり、新大陸へ踏み出したヨーロッパ人の必携書を著した人物でもありました。自分とは異なる背景をもつ「他者」に対して、ヘーロドトスが「驚嘆(タウマ)」に衝き動かされてさかんにアプローチし、「他者」といかにかかわってゆくかを実地に示したことが与って大きかったようです。その彼が共感の難しい対象を描き出す文体を磨き上げ、その集大成である作品を生み出した以上、私が彼に絡め取られてギリシア語を学び始め、いまこうして、彼の著作を繙いてあれこれと思いをめぐらせているのも、当然であったと言えましょうか。
必然の歩み
ギリシア人は「逃れがたい定め」を「アナンカイアー?テュケー」と言うことがありました。直訳すれば「必然の運命」です。しかし二つ目の単語、テュケーは「偶然」を意味する単語でもあります。必然と偶然とは一見するにそりの合わない言葉です。木田元先生の『偶然性と運命』(岩波新書新赤版724、2001 年)には、あとから振り返って出来事を見直し、整理した時に「運命であった」という感慨が生じるということが述べられています。当事者がことの渦中にある時、すべては偶然でなりゆき任せに見えるものですが、終わってみれば、すべてが一本の筋で繋がっているように感じられるということです。先のギリシア語はそうした機微を表現したものでしょう。私が古代地中海世界、とくに古代ギリシアの言葉や文化に首をつっこむようになった小さな遍歴も、振り返ってみれば、共感に対する警戒心がたぐり寄せた全くの必然、あるいは運命であったと言わねばなりません。
共感の重要性が叫ばれる昨今です。共感できないことが多々、身の回りに存在しているからこその叫びであり、しかし共感できないものとなんとかして分かりあっていかねばならない事態に立ち至っているがゆえの訴えです。私はヘーロドトスをはじめとする、古代ギリシア文化と出会い、共感について考えるきっかけを偶然手に入れることができました。もちろん、みなさんにもチャンス(=チュケー=偶然)はあります。「驚嘆(タウマ)」、あるいは「野次馬根性」を大切にし、他者と立ち混じることを恐れず、むしろこれを喜ぶ気風は、遠く古代ギリシアに端を発する人文学の長い伝統を継受し、コース制という特徴を活かした文芸学部の四年間でも培うことができるはずです。その気風が人生に生起する色々な不思議を理解する鍵になるのものと信じます。みなさんは文芸学部でどんな偶然と巡り合うことになるのでしょうか。無数の偶然の中で、色々なことに挑戦していただきたいと思います。それはいつの日にか、みなさんのかけがえのない(= 必然的な)人生をみのり豊かなものにしてくれることでしょう。