
家政学部 被服学科ニュース詳細
更新日:2025年07月28日
授業紹介
被服学科専門科目「被服造形基礎実習」を紹介します
1年次対象の被服学科専門教育科目「被服造形基礎実習」では、前期に洋裁と和裁の基礎知識および縫製技術を学びます。課題作品として、洋裁ではミシンとロックミシンを用いた「ショートパンツ」、和裁では手縫いによる「肌襦袢」(着物用下着)を制作します。
洋裁では、ミシンの操作に慣れるため、まず基礎縫い課題に取り組みました。まっすぐ縫う?曲線を縫う?角を縫うといった基本動作を繰り返し練習し、ミシンへの苦手意識が少しずつ払拭され、作品制作にも自信をもって取り組めるようになりました。当初はミシンの操作に苦戦していた学生も、回を重ねるごとに手元の動きが安定し、次第にミシンの音にも耳を傾けられるようになりました。
基礎縫い課題を経て、ショートパンツの制作に取り組みました。生地は各自が手芸店などで気に入ったものを購入し、型紙作成、印付け、裁断、縫製、アイロンがけまで、各工程を丁寧に学びながら完成を目指しました。完成品を並べてみると、同じ型紙を使っていてもそれぞれの個性が反映され、まさに「世界に一つだけの一着」となりました。
和裁では、晒し木綿の生地を長方形に裁断し、へらを用いてしるしをつけました。縫製はすべて手縫いで行うため、指ぬきを使用した「運針」(並縫い)の練習から始まり、肌襦袢の制作を通してさまざまな縫い方を習得しました。授業の前半では思うように針が進まず苦労する場面もありましたが、後半になると手の動きも滑らかになり、集中力と達成感を感じられるようになりました。完成した肌襦袢には、それぞれ好みのレースやリボン、刺繍などを施し、オリジナリティあふれる作品となりました。授業最終日には、自作の肌襦袢を着用し、浴衣の着付けを行いました。
「被服造形基礎実習」で修得した知識や技術は、その後の被服学科専門教育科目「被服造形実習I?II?III」や「伝統和服制作実習I?II」へとつながり、卒業研究における高度な作品制作へと発展していきます。

|

|

|

|

|

|
 |
 |
 |
|
オリジナル装飾の様子 |
||

|


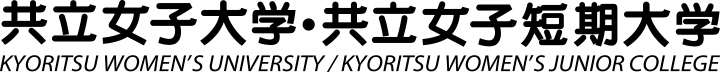




![家政学部[被服学科]](/img/academics/undergraduate/kasei/hihuku/title_vi.png)
![家政学部[被服学科]](/img/academics/undergraduate/kasei/hihuku/title.png)