
Faculty of International Studies
国際学部ニュース詳細
更新日:2025年02月14日
学生の活動
【国際学部】学生広報委員による先生インタビュー⑦ ~高野先生編~
皆さんこんにちは。学生広報委員の宮地理子です。
国際学部の先生方に「20代前半は何をし、何を考えていたのか」インタビューする企画の第7回は高野麻衣子先生にインタビューしました。
.jpg)
Q1. 大学時代は何を学んでいましたか?その分野を専攻にしたきっかけはありますか?
筑波大学の比較文化学類で北米の歴史と社会を中心に学んでいました。とくにカナダに関しては、中学?高校の世界史でカバーしきれないため、ご専門の先生から学ぶことの一つ一つがとても新鮮だったのを憶えています。先生は、「何かに必死になるなら今だ」と繰り返しおっしゃっていました。その言葉に鼓舞されて、大学3年の夏に1カ月間、バックパックを背負ってカナダを一人旅し、地域的?民族的多様性とそこから生み出される活力に触れたことが、カナダ研究を専攻するきっかけになりました。
かつてイギリスとフランスの植民地であったカナダは、英語とフランス語の2つを公用語としていますが、多文化主義のもとであらゆる文化を対等に位置づけ、尊重しています。フランス語圏のケベック州をはじめ、各地域には独自の社会的?文化的豊かさがあります。ただし、こうした豊かさと併せて、潜在的な地域間?民族間の利害対立があり、20世紀後半にはケベック州において分離?独立運動が起こりました。カナダについて学ぶにつれ、このような地域的?民族的利害が歴史的にどのように調整され、どこに妥協点が見出されてきたのかに関心を抱き、研究テーマになりました。
一人旅では、文献だけでは得られない、現地の人々に話を聞いたからこそ気づいた視点が多くありました。実際に自分の足で現地へ行き、積極的にコミュニケーションをとる必要性を実感しました。加えて、フランス系の人々とのコミュニケーションでは、言語の尊重に対する繊細な感覚を養うことができました。卒業論文では、ケベック州の分離?独立問題をテーマにし、現地の大学図書館で収集した選挙区ごとの州民投票のデータをもとに、分離?独立に対する州民の意向実態を分析しました。
カナダをもとに、多様な利害の調整と妥協のあり方について学ぶことは、自分自身にとっても、社会生活におけるバランス感覚を身に着ける上で役立つと考えています。例えばゼミの運営においては、学生の皆さんそれぞれの興味?関心やこれまでの経験が異なる中で、どうすれば楽しく有益な学びの場になるのかを考える上でカナダ研究が大いに役立っています。
.jpg)
Q2. 大学時代に力を入れて取り組んでいたことは何ですか?
ジョギングサークルに所属し、週2回の活動やマラソン関係のイベントに参加していました。もともと走ることが好きだったので、個人でも毎日のように大学周辺を走っていました。ジョギングをしている間は無心になれて、頭の中がリセットされるので気分転換に最適でした。20代の頃は勉強や進路など悩みも多く、何か目標を持てばスランプに陥ることもありましたが、走ることがそこから抜け出す術になるという気づきを得ることができました。
Q3. 将来の夢は何でしたか?また、当時の不安や悩みがあったら教えてください。
当時は不況で、就職氷河期でした。英語の教職課程を履修していたので、英語の教員として専門性を高めつつ安定を目指すか、あるいは新しく関心を持ち始めていたカナダの研究を続けるために大学院へ進学するか悩みました。周りが就職する中で、研究者として本当に食べていけるだろうかという不安は大きかったです。それでも、初めて一人旅をしてカナダに魅了され、夢中になれる分野が新たに見つかり、ここでやらなかったら後悔するという思いから進学を選びました。
大学院時代に出会った先生方は、一人の研究者を養成するためにとても熱心にご指導くださいました。先生方が話される内容の一つ一つが貴重な学びであり、全てを吸収しようと必死にメモをとっていました。また、研究について語り合える素晴らしい仲間にも恵まれました。出会った人々との関わりと自分の中にある知的好奇心が、研究者になるという夢を実現させてくれたと思います。
.jpg)
Q4. 現在の職業までの経緯を教えてください。
大学院では、アメリカ政治?政治史の先生方にご指導いただきました。そのため、アメリカをはじめとする他国との比較の中でカナダを相対化し、より良い理解につなげるという研究方法を身に着けることができました。また、比較によって知的関心の幅を広げることができました。
研究者を目指していたので、共立女子大学に着任する前には非常勤講師としていくつかの大学で、そして民間の語学学校でも教えていました。他大学の体育学部で教えていた時には、学生の皆さんの活力に圧倒されながらも、目標に向かって必死に取り組む彼らの姿勢から大いに刺激を得ましたね。
このような過程を経て、2016年に共立に着任しました。授業で重視しているのは、学生の皆さんとの対話です。学生さんは皆、様々な潜在能力を持っていますが、教員はそれを直接的に見られるわけではありません。こちらから問いを投げかけ、皆さんから自分の考えを積極的に出してもらうことで、この潜在能力を引き出すことができると考えています。卒業論文の指導では、対話を通じて論文の問いを設定することに最も時間をかけています。1年間かけて何を調査し、どのような結果を得るのか、軸を決める上で問いの設定はとても重要だと考えるためです。
Q5. 学生時代にやっておけばよかったことはありますか?
国内旅行です。学部時代はつくばにこもっていました(!)が、大学には全国各地から学生が集まっていたので、仲間から各地域の自然や文化について話を聞くことが多かったです。今からでも、例えば東北や山陰地方などを自分の足で歩いて見て回れたらと思います。
.jpg)
Q6. 私たちが学生時代にやっておくべきことはありますか?
行きたい場所へ行き、自分でその地域に触れることです。社会人になると時間の制約もあり、物事に優先順位をつけることが多くなりますが、学生時代は自由度が高く、目の前に広がる光景をありのままに見て、吸収することができる貴重な時期だと思います。そこから、卒業論文のテーマや将来の進路に気づきを得られるかもしれません。
Q7. 国際学部の学生にメッセージをお願いします。
何かを「語る」ことができる人はとても魅力的だと思います。勉強や経験を通じて物事を語ることができれば、人間的に豊かになるのではないでしょうか。自分の興味?関心を見つけ、多くを学び、経験する4年間にしてもらえればと思います。
.jpg)
今回のインタビューを通して、問いを投げかけることで学生の潜在能力を引き出すことができるというお話が印象的でした。先生のカナダの人々との関わりを含めて、コミュニケーションは相手を知るだけでなく、能動的に考え、自分を知るということにも繋がると思いました。コミュニケーションをとおして得られた気づきが知的好奇心を育み、新たな問い、学びへと広がっていくことでしょう。
私自身、まもなく卒業の時期を迎えますが、4年間の学びと経験を振り返り、自分は何を語ることができるのか、考えてみたいです。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
↓↓ GSEプログラム特設サイトは以下からご覧いただけます ↓↓.jpg)
↓↓ 国際学部の情報は以下からもご覧いただけます ↓↓


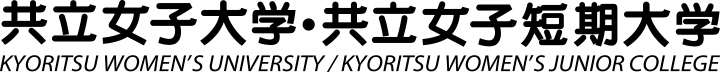





.jpg)
.jpg)